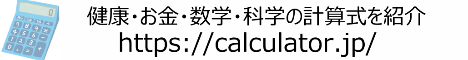前回、ストレスについての記事(https://sensaikousatu.com/what-is-stress/)でストレスの対処法の中の一つとして発想の転換はストレス耐性につながるということをお伝えしました。今回は詳しく、その発想の転換の仕方や考え方を解説していきます。
リフレーミングとは?

発想の転換をすることをリフレーミングといいます。
発想を変えるというと、創造性、斬新なアイデア・・・?なんだか限られた人ができるような難しそうなものに聞こえるかもしれません。
リフレーミング(reframing)の「re」は「リフォーム」や「リトライ」などのように、「再び」という意味があります。「フレーム(frame)」は、枠、縁という意味なので、合わせると「再び枠組みをする」といった意味合いになります。眼鏡のフレームが変わると顔全体の印象が変わるように物事の枠組みも色々な角度で変えるということです。
いつもの自分の物事の見方や考え方を、別の面で見てみたり違う視点で考える、ということです。似た言葉で「ポジティブシンキング」というのがありますが、こちらはすべてポジティブ、前向きに考えるため、場合によっては無理やり感が出てきてやっていて限界を感じてしまうのですが、発想の転換(以後「リフレーミング」で統一します)はポジティブな面だけではなくあらゆる可能性、視点で物事を見る、相手への理解につながる点で相違があります。
例えば、
「仕事でミスをして上司に怒られた」とします。
【ポジティブシンキング】・・・「よくあることだから大丈夫!この仕事にはミスはつきものだから気にしないで次行こう」
【リフレーミング】・・・「ミスをするということはまだ改善の余地がある、伸びしろがあるということ」「もっと大きなミスをする前に気づけてよかった」「もし上司だったらどう対処するか」「お客様の立場だったらお金を払ったのに損害を被ったことになる」「このミスから得られたことは何か」など
リフレーミングだと多角的に考えるので、問題の解決の思考や相手の立場で考えられて学びを得られたりします。
リフレーミングのメリット・デメリット

| メリット | デメリット |
|---|---|
| あらゆる視点で物事を考える力がつく 視野が広がり柔軟性がもてる 引きずらずに切り替えできるようになる ストレス耐性が高められる コンプレックスが軽減される 相手の理解につながり、寛容になれる 新しいアイデアを思いつきやすくなる 反省の質が高くなる | いろいろ考えすぎて前に進めなくなる場合もある 一つ一つにしていると時間がかかる →即決を求められる時に難あり 思考をよく使う |
総じてメリットの方が多く、デメリットである「時間がかかりがちであること」と「脳をよく消耗する」という点を差し引いてもリフレーミングをしないことによる損失の方が大きいかなと思われます。
リフレーミングの仕方
まず、リフレーミングをするにあたって、いつも自分が物事や人に対して、どのように捉え考えているかを認識しておく、できれば紙などに書いて残しておくと、自分の思考の癖やリフレーミング後の変化に気づくことができるのでおすすめします。
リフレーミングに“こうしなきゃいけない”というのは特になく、基本的に自由です。ですがそうお伝えして終わると、やったことがない人にしたら漠然としてどうしたらいいかわからないと思うので、いくつかの視点とそれぞれのポイントをご紹介しておきます。
一つの事柄について、それらに沿って考えていくと様々な視点が見えてくるはずです。
例A)「転職活動で200社応募したが不採用が続いた」
【リフレーミング前の心境】
→「いろんな人から自分は価値がないと否定されたような気分」
「仕事が見つからなかったらどうしよう、不安」
1.今の状況よりもっと最悪な状況を考える
「求人募集が一切ない」「採用されたと思ったら架空の会社だった」「一社面接を受けるのに1万円払わなければならない」※ありえないことでも今抱えている問題・悩みよりうんと悪い状況を挙げていくことで、それよりはずっとマシじゃないかと考えやすくなります。
2.環境が変わったらどうか
「200社も受けるほどの根気強さ、不採用が続いても折れないバイタリティはきっと営業の新規開拓や研究職など、すぐに結果の出ない地道な仕事の場面で重宝するだろう」
3.この状況の意味を考える
「受ければ受けるほど場慣れして面接官の同じような質問に上手く対応できるようになっている」「もっと多くの企業を受けて自己アピールの仕方を磨いたり、会社をしっかり吟味しなさいということかな?」
4.相手の立場
「自分が人事だったらたくさんの応募者の中から選ぶわけだからそんなに時間をかけていられないだろうし、その限られた時間の中で何を見るだろう?」「自分に何ができるかを十分に伝えきれていないし、積極的に質問もしなかったので、会社にふさわしい人物像だと感じられなかったのかもしれない」
5.乗り越えたら何が待っているか
「これだけ多くの企業を受けてきたので入社できたのなら入社できたありがたみを噛みしめて働ける」「忍耐強さやバイタリティが強くなっているだろう」
6.過去に同じような出来事はあったか・あったとしたらどう乗り越えてきたか
「今回が初めて」・・・働く前に社会の厳しさを身をもって体験することができた。この経験を通ってきたからこそ学べたことがあるし、今の自分がある
「以前にもあった」・・・以前は150社くらい受けて不採用だった。でもいつか自分を採用してくれるところは絶対あると信じて面接練習や履歴書の改善を繰り返し、ちゃんと乗り越えてきた。今回は初めての職種に挑戦するから前回より間口が狭いのは仕方がない。でも前回と同様に自分を信じてめげずに臨めばきっと今回も乗り越えられるだろう。
7.この出来事がなかったら
「安易に入社してしまい、合わない職場ですぐ転職してたかも」「自己分析も進まなかっただろうし、ビジネスマナーも本気で身に付けようとも思えなかった」
8.励ましの言葉をかけるとしたら?
「不景気だし、200社受けても採用されないなんてざらにあるさ」「人事があなたの良さを見抜けていない」「不採用だからと言ってあなた自身が否定されたわけではない」
9.ポジティブな人だったら?他の人だったらどうするか?
「大丈夫!人間、前を向いていたら必ず道は開ける」「応募するエリアや条件を広げてみたらどうだろう」
例B)「言い方がキツイ先輩にいつもへこむ」
【リフレーミング前の心境】
→「言い返したくなる時もあるし、泣きたいくらい悲しい時もある。キツイこと言われるたびにストレスだしモチベーションが下がる」
1.今の状況よりもっと最悪な状況を考える
最悪な状況:「言い方がキツイ上に手が出る、傷を負う」「先輩だけではなく同僚も後輩も顧客もみんなキツイ言い方で責め立てる」→今の方がマシ!
2.分析してみる
言われたことすべてがキツイ言い方か?
〈Yes〉→方言やイントネーション、生育環境が原因だとしたら、先輩としては別に責めたり怒っているわけではないのかも。
〈No〉→振り返ってみれば、一歩間違えれば怪我になってたことにはキツイ言い方をされてたな。戒めとしてあんな言い方をしたのかも」「通勤途中、工事現場からべらんめえ調の大きな声が聞こえてきたけど、それが他の職場でもよくあることなのかな。あのべらんめえ調に比べたらまだいい方だ」
3.相手の真意を推測
「他の人には何も言わないでほぼ放置だけど自分にだけ言ってくるということは期待されている証拠だな。だって見捨てられてたらあんなに言わないでしょ。」「もし気分によるものなら重く受け取るのはもったいない、いちいちそれで感情を振り回されるは時間と労力の無駄だから、「今日は機嫌悪いのね」くらいで流していこう」
4.この状況に置かれている意味を考える、価値を見出す
「これだけキツイ言い方されても耐えている自分がいる。自分って結構打たれ強いんじゃない?これから心ないことを誰かに言われたりしてもちょっとやそっとじゃ動じないメンタル作りに一役買ってくれてると考えたら感謝さえ湧いてくる」
5.今の状況をどう生かせるか
「反面教師のように、どういう言葉や言い方が人を傷つけるか、身をもって経験したからこそ、自分は人にはそのような言い方はしないようにしようと思える」「キツイ言われ方をされた人の気持ちが分かるので、同じ境遇の人に共感できる、寄り添える」
リフレーミングをするにあたって

リフレーミングがすべてに有用とは限らず、例えば「仕事の評価が公正にされていない」や「パワハラなどを受けている」ならリフレーミングより、相談したり、どこかでストレス発散したり、それでも変わらずつらい日々が続くようなら退職を考えるなど、場合によっては問題解決や他の対処の方が良い場合もあります。
色々視点を変えて考えてみて、気持ちが楽になったりストレスが軽減されて気にならなくなってきたのならリフレーミングが上手く発揮されているということですし、やってみてもストレスや悩み、問題があまり変わらないなら問題解決に動くなど対応していきます。
症状に対して効果を発揮する薬があるように、「一杯飲んでストレス解消すればまぁやっていける」ことなのか、「思い込みや固定観念によって悩んでいるかもしれないからリフレーミングしてみよう」なのか、問題解決できることなのかなど、対処していくうちになんとなくわかってくるでしょう。
また、「言われなくてもわかってるよ」と思うかもしれませんが、問題解決として「退職」や「離婚」など思い切った行動に出る前にはリフレーミングやアサーション、ストレス解消法などを試してみて、それでもどうしてもダメならの最終手段にする方がいいでしょう。
より効果的にするために
いつも同じような思考回路、または、他の視点が思い浮かばないという人は、日頃からどんなことでも(好きなジャンルから入るのも手)物事に対して色々な視点で考える癖をつけていくことや、あらゆる知識や情報を吸収するようにすると、いざリフレーミングをする時に質の良い発想が生まれたり、考え方にもバリエーションが出てくると思います。 なるべくたくさんの視点で考えるとそれだけ視野も広がり、リフレーミングのメリットを得られやすくなります。
リフレーミングすることの意義や重要性
もし自分が一つや二つ程度の少ない側面だけを見て、それがネガティブなものだったら、挑戦しようとしていたことを止めてしまったり、相手との関わりを絶ってしまったりする人もいるかもしれませんが、それは同時に、あらゆる可能性やチャンスを失っているかもしれないということにもなります。
情報を吟味する
私たちは情報過多の社会にいますが、例えば「最高(上限)30万円までキャッシュバック」という宣伝文句をどう捉えるでしょうか?
“えっ30万!?これは申請しなきゃ”とすぐに飛びつきますか?
それとも、
“でも待って。最高(上限)だから満額キャッシュバックされることってあまりないんじゃ・・・審査や手続きがあるみたいだし、実際の金額が分からない以上は良く考えた方がいいかな”
と慎重になりますか?
広告は言葉巧みに表現されます。私はこれもリフレーミングの一種ではないかと思っています。
嘘ではないけど良い部分をうまく魅力的に表現して惹きつける。それならこちらも裏をかいてリフレーミング、視点を広くもって対応しましょう。
陥りがちな思考
“手術に成功する確率50%”だったらどう考えますか?
“50%も失敗するリスクがあるのか・・・怖いな、どうしよう”
なのか、
“半分の確立なら賭けてみよう”
となるのか・・・。
50%という事実は変わらないけれど、私たちは自分に都合のいいようにポジティブに解釈することがあれば、ネガティブな面に引きずられてしまうこともあります。偏らずに包括的に捉えたうえで判断したいものです。
自分で考えることの大切さ
思考することを疎かにしていませんか?
言われたからそうしている、みんながそうしているから自分もする。
子供の頃、中学生くらいまでの私がまさにそうでした。周りと違っていたらいじめられるというのがあってランドセルも絶対に赤、みんなと足並みをそろえる、意見も言えない子供でした。
でもそうしていると、やはりそこから抜け出そうとしたときに自分はどうしたいんだろう?本当の自分は?という迷子に陥ります。(今はその反動もあってか人と違うことを好む、正反対の性格になりましたが)
自分で考えていく、他人志向ではなく、かといって他人の意見を一切聞かないということではありませんが、自分志向でいく。そうでないと他人に振り回されてしんどくなってしまいます。
多数決というのはこわいですね・・・。私は他人志向を助長している気がしています。それで少数派は納得するのだろうかと疑問に思います。歴史的に見ても少数派が革新的な発明や発見、人類の進化発展に繋がっていることは多々あるので、支持者が多いから正解とは限らないということがわかります。多数決で決めてしまっていいことといけないこと、使い分けて適切に判断したいものです。