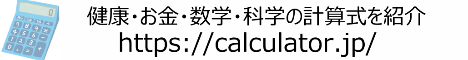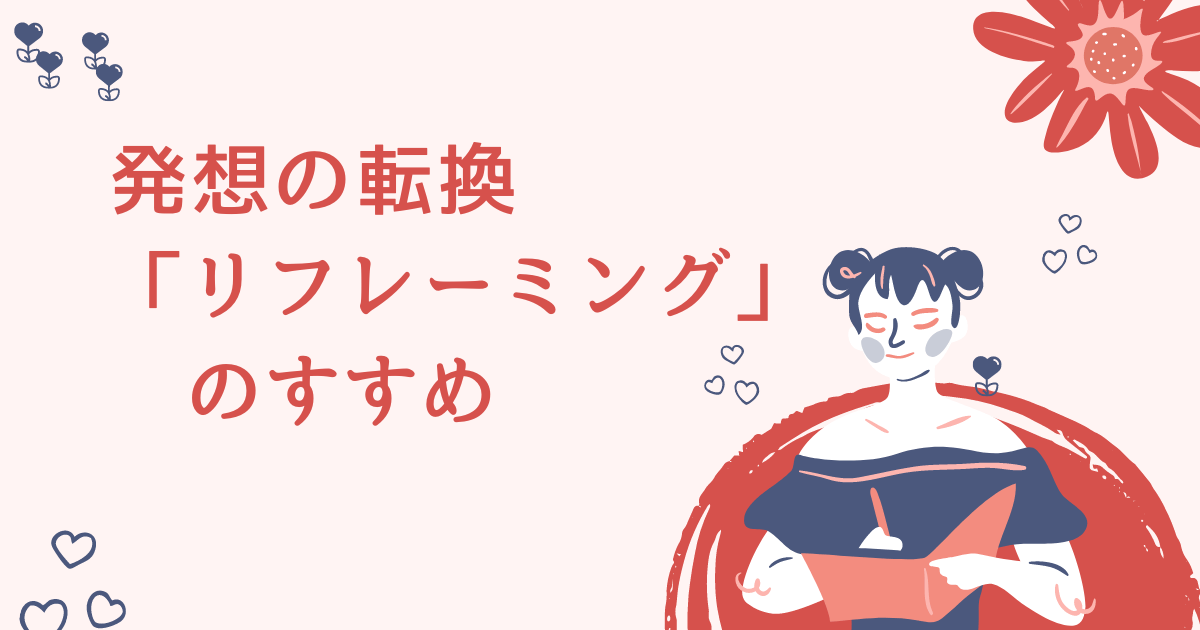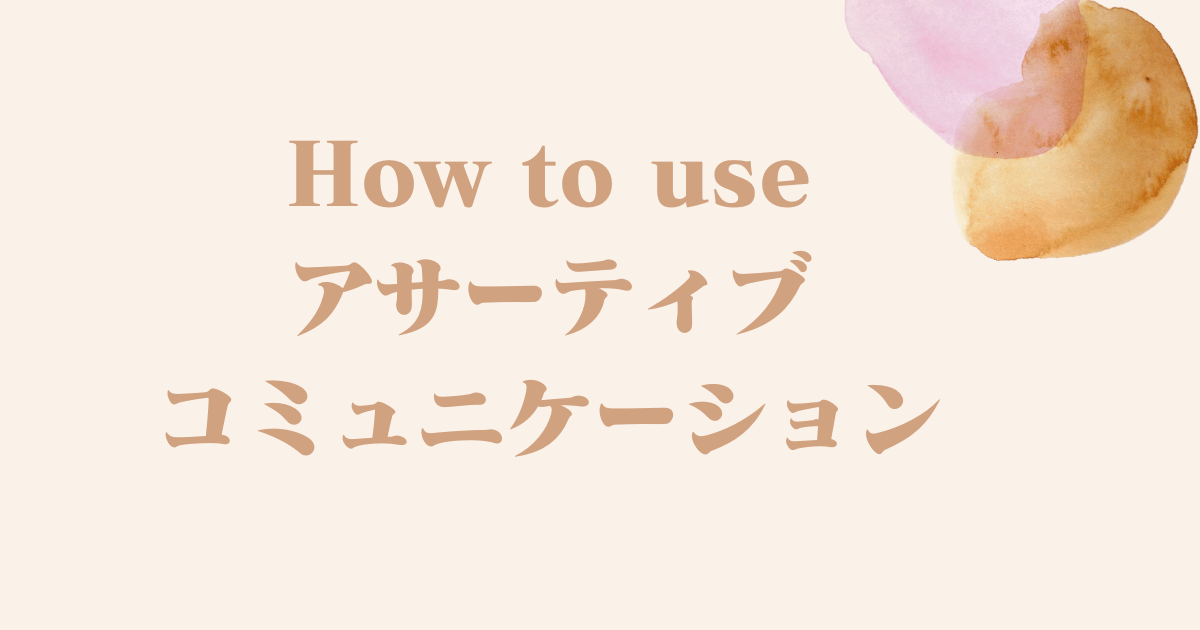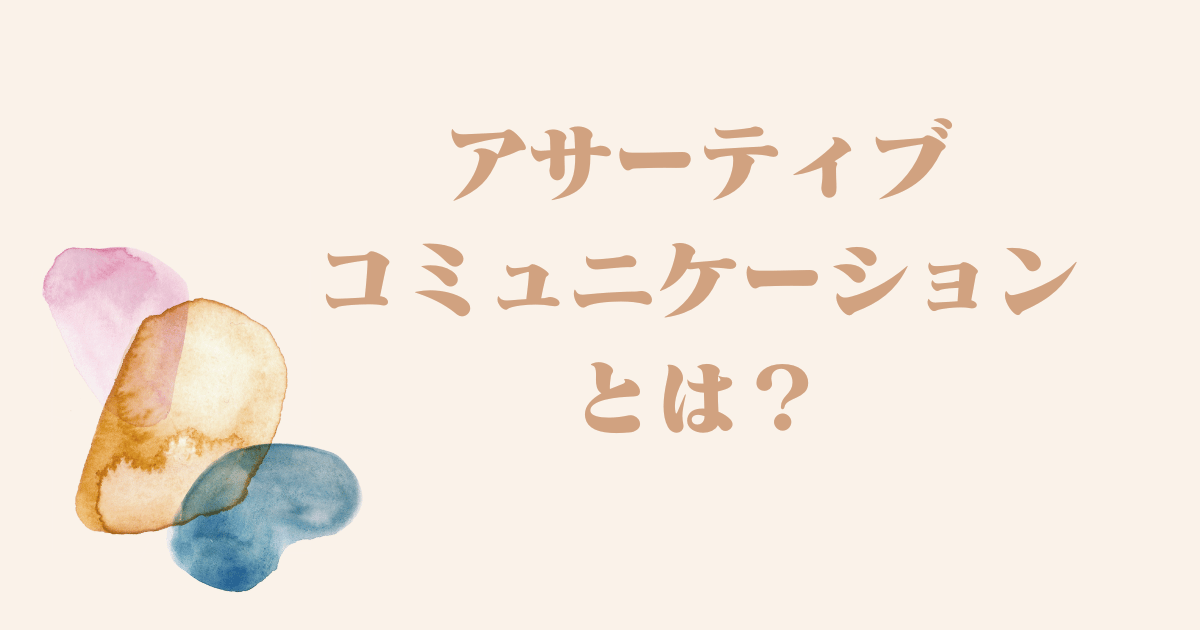自律神経とは

自立神経とは、「交感神経」と「副交感神経」からなり、2つのバランスをうまくとって、からだの調子をコントロールし、正常な機能を維持する働きをもつ神経です。
その自律神経の働きが乱れ、からだの機能が正常に働かなくなった状態は自律神経失調症を招きます。
交感神経と副交感神経は相反する働きを持ち、一日の中で交互に優位になり、どちらかにずっと偏るということなくバランスを保つことで生活リズムを作っています。
【交感神経】:活発になると、それに伴って身体機能も、心拍数は速くなり瞳孔も大きくなったりして興奮モード、活動的になります。
【副交感神経】:優位に働くと、呼吸は落ち着き瞳孔は小さくなったりして、睡眠時や入浴時、食事の時のようなリラックス状態になります。
| 交感神経 | 副交感神経 | |
| 〈心拍数〉 | 増加 | 減少 |
| 〈血管〉 | 収縮 | 拡張 |
| 〈瞳孔〉 | 拡大 | 縮小 |
| 〈消化器〉 | 抑制 | 促進 |
| 〈泌尿器〉 | 畜尿 | 排尿 |
バランス、メリハリが大事

《交感神経》が優位の状態が続くと・・・
いつも『興奮・活動モード』『緊張状態』が続くということなので、やはり身体は休まらず慢性的に疲労します。具体的には、汗をかく、消化器は抑制されて消化不良、血圧が上がる、血管は収縮されて血流が悪くなる、倦怠感などが症状として出てきます。精神面にもイライラや不安感、気持ちの低下など、影響を与えます。
《副交感神経》が優位の状態が続くと・・・
心拍数は減少し、血圧が下がる、血管は拡張するので血流がよくなり、消化器は促進されて消化が活発になる等、一見良い状態に思えますが、過剰になると脳や心がリラックスしすぎて勉強や仕事などの集中すべき時に頭が働かず、眠気が強くなったり、無気力、活動力が低下してしまう、低血圧などといった症状になるおそれがあります。
仕事の時に頭がボーっとして、夜眠る時に目が冴えても困るね


自分の意志で自律神経そのものをコントロールはできないけど、うまく働くように間接的に整えることはできるよ
自律神経が乱れる原因
自律神経が乱れる原因としては、下図のような要因が挙げられます。


①ストレス
ストレスにも様々な種類があり、身体を酷使して肉体的に加わるものもあれば、季節の変わり目やライフイベントなどの環境変化によるもの、対人関係などによる精神的なもの、女性は月経周期、更年期によるものなどがあります。(※ストレスについてはこちらの記事(https://sensaikousatu.com/what-is-stress/)で詳しく解説しています。)
②生活習慣
日ごろの生活習慣、ライフスタイルも自律神経のサイクルに影響を及ぼす一つとされています。
【食生活】
質(ジャンクフードや栄養バランスの偏った食事)、回数やタイミング、食べる速さ、食事量(食事抜きや食べすぎ等)があります。
私たちは食事をすると副交感神経優位になります。食後に眠くなるのは副交感神経が活発に働くことでリラックスモードになるためです。
眠くなるからといって食事を抜く方もいますが、血糖値が急激に下がり、飢餓状態になって代謝が下がるなど、身体に負担となってしまいます。
【運動不足】
いつも空調の効いた室内で汗をかかないでいるのもよくありません。運動をすることで代謝が上がり汗をかき交感神経を刺激します。筋肉をつけることでストレス耐性が高まったというデータもあり、ストレス対策にもいいとされています。
【スマホやPC】
電子機器から放出される『ブルーライト』は睡眠の妨げになってしまいます。目の奥まで入りダメージを受け、特に寝る直前に見たりしていると睡眠の質が下がると言われています。見ないことが一番ですが全く見ないわけにはいかないと思うので、ブルーライトをカットする設定やアイテムを使用するといいでしょう。
【好きなこと・趣味】
何か夢中になれるもの、趣味がないのも気持ちもなかなか上げられず、交感神経が働きにくくなります。
【日光浴】
日光を浴びることは、自律神経、生活リズムを整えるうえで助けとなります。
【カフェイン・タバコ・アルコール】
とり過ぎも睡眠の質を下げたり不眠のもととなります。
③生活リズム
生活リズムの乱れ=自律神経の乱れとしてもいいくらい密接です。もっといえばストレスと生活習慣と生活リズムの乱れもお互いに影響し合っています。
夜勤、深夜労働、早朝出勤など労働条件によって不定期だったり、夜遅くまで起きて昼間まで寝てしまう生活が続くと、やはり自律神経は狂っていきます。寝不足が続き、生活リズムが乱れると、気分が落ち込みやすい、イライラしやすい、思考力の低下などの精神面での影響や、だるさや頭痛などの身体の疲労感にもつながっていきます。
また、寝不足生活が続くと認知症のリスクが高くなるという研究データもあります。
④ホルモンバランス
ストレスや不規則な食生活、過度のダイエット、更年期などによりホルモンバランスが乱れると、自律神経も影響を受けます。これは、脳の『視床下部』という部位がホルモンの分泌と自律神経のコントロールしているためです。
HSPは自律神経が乱れやすい


原因を読んでお察しがつくかもしれませんが、HSPは自律神経が乱れる要因に関連する気質を含み、要注意なのです。なぜなら、特にHSPは人との関わりや周りの環境・変化などに敏感で疲れやすくストレスを溜めやすいと言えるからです。
ストレスを敏感にキャッチすると、例えば
①言われたことが気になって眠れない→②スマホで検索したり悩む→③寝不足→④日中眠くてだるい、思考が働かない→⑤うっかりミスする→⑥嫌味を言われる→⑦凹む(①へ)
上記のような負のスパイラルに陥ってしまう可能性が高いです。
ストレスを感受してなかなか切り替えられずに睡眠に影響、眠れないことで身体も精神にもさらにストレスダメージとなり食生活の乱れや興味の喪失などにつながりかねません。
HSPの他にも、
・完璧主義で几帳面
・負けず嫌い
・ストレス過多
・頑張り屋さん
・あまり健康に気をつけていない
・日中に外に出たり運動する機会がない
などの性格や状態の人は自律神経が乱れやすいと言えるでしょう。
自律神経を整えるために


自律神経を整えたい人は早い話、先ほどご説明した自律神経が乱れる原因を絶てば良いわけですが、一つずつ見ていきましょう。
①ストレスに対して
ストレスとうまく付き合う(自分に合う発散法を持つ、モチベーションに変える)
考え方・捉え方を変えて引きずらない切り替え上手になる
深呼吸して呼吸を整える
睡眠を十分にとる
心地よいものを取り入れる(肌触りの良いものや音楽など、五感から受ける刺激)
好きなことをする
よくモーツァルトの曲や〇〇ヘルツの音楽が良いと言われていますが、実体験を踏まえて個人的には自分が好きな音楽が一番心身に良いと思っています。
音楽に限らず健康に良いとされているものも、我慢してストレスになるよりは自分の好きなもの、興味のあるものを選んで適度に取り入れた方が結果的には良いのかなと。
②生活習慣に対して
自律神経のサイクルを乱す悪習慣を改善する。具体的には、
栄養バランスと腹八分の食事、変則的に食べない
よく噛んでゆっくり食べる
寝る3時間前は何も食べない
定期的な運動、ストレッチ、
カフェイン・アルコール・タバコを控える
シャワーだけで済まさずにぬるま湯のお風呂に浸かる
寝る前のスマホやPCを絶つ
日光に当たる
活動モードとリラックスモードのメリハリを意識する
③生活リズムに対して
(夜勤など不規則な労働環境で自律神経を整えることを優先させたいのであれば)転職などで労働環境を変える
夜にしていることを日中に回して寝る時間を確保する
体内時計を整える(朝起きたら朝日を浴びる、決まった時間帯に食事、寝る時は部屋を暗くする等)
朝に起きる
④その他
アロマオイル、お香などの香りの効果を利用する


香りも人によって好みがありますが、参考までに香りの種類と効果をご紹介します。
アロマの種類
1.【ハーブ系】
スッとした清涼感のある香りで頭をスッキリさせ、リフレッシュや集中力を高めるものが多い。
ペパーミント(薄荷)、ローズマリー、ユーカリ、オレガノ、タイム、スイートマジョラム、メリッサ、フェンネルなど
2.【柑橘系】
馴染みのある柑橘類の爽やかな香り。気分をリフレッシュさせるものが多い。
レモン、レモングラス、オレンジ、ゆず、ライム、グレープフルーツ、ベルガモットなど
3.【オリエンタル/エキゾチック系】
インドや中東、東南アジアを思わせる異国的情緒のある香り。重厚な甘い香りをもつものや、深く重みのある独特な香りが特徴。
ジャスミン、パチュリ、イランイラン、サンダルウッド(白檀)、パルマローザ、ベチパーなど
4.【樹木系】
森林を彷彿させる、樹木の深い香り。緊張感や不安、イライラなどを和らげる作用のあるものが多い。
サイプレス(ヒノキ科)、ヒバ、スギ、シダーウッド、ジュニパーベリー、ローズウッドなど
5.【樹脂系】
木の樹脂を抽出してできる、甘さや重厚感のある独特な香り。
フランキンセンス(乳香)、ミルラ(没薬)、ベンゾインなど
6.【スパイス系】
香辛料のような鋭く刺激的な香り。辛さや甘さを感じるものもあり。
ブラックペッパー、シナモン、バニラ、ターメリック、ナツメグ、クローブなど
7.【フローラル系】
お花から抽出される、優しく華やかでエレガントな香り。気分を明るくし女性に人気のあるものが多い。
ラベンダー、カモミール、ローズ、ゼラニウム、ネロリなど
作用・効果
睡眠の質を高めたい
・ラベンダー
・サンダルウッド
・ジャスミン
・カモミールローマン
・スイートマジョラム
・オレンジ
・ローズなど
集中力や記憶力を高めたい
・ローズマリー
・ユーカリ
・ティーツリー
・ジュニパーベリー
・レモン
・グレープフルーツなど
リフレッシュして前向きになりたい
・柑橘系
・ティーツリー
・バジル
・スペアミント
・パイン
・タイムなど
眠気を取りたい
・ペパーミント
・ローズマリー
・グレープフルーツ
・ジュニパーベリー
・ユーカリなど
イライラやストレスを鎮めたい
・フランキンセンス
・ラベンダー
・ジャスミン
・イランイラン
・カモミールローマンなど
リラックスしたい
・ベルガモット
・バニラ
・サンダルウッド
・クラリセージ
・スイートマジョラム
・ラベンダーなど
食欲がない
・ブラックペッパー
・シナモン
・ジンジャー
・カルダモン
・メリッサ
・ローズマリー
・レモングラスなど


今の自分の状態にあった香りや好きな香りをブレンドするのもいいね
ツボ押し
ツボを知っていればちょっとしたスキマ時間に気軽に自分でできるのでおすすめです。イタ気持ちいい程度に押します。
自律神経を整える効果のあるツボ
1.外関(がいかん)
手の甲側の、手首から指3本分の場所にある凹み部分。
2.神門(しんもん)
耳の上部にある、Y字にくぼんでいるところ。押すというよりは、くぼみ部分をつまんで斜め上に引っ張るように刺激すると良い。
3.百会(ひゃくえ)
両耳と鼻をまっすぐ上にたどって交差した、少し凹みのある場所。百もの多くの気が行き交うところとして、『万能のツボ』ともいわれる。
4.合谷(ごうこく)
親指と人差し指の、骨の交わる部分の人差し指寄りのくぼみ。こちらも『万能のツボ』として知られている。
5.労宮(ろうきゅう)
手のひらの中心にあるくぼみ部分。
6.湧泉(ゆうせん)
足の指を内に曲げるとできるくぼみ部分。
7.内関(ないかん)
手のひら側の、手首のしわから指3本分のところにある。
ストレッチ・ヨガ


呼吸法に合わせてポーズをとり、背中を伸ばしたりからだをねじったりするので、交感神経優位で緊張・凝った筋肉をほぐしリラックス効果をもたらします。
1.【猫のポーズ】
四つん這いになり、猫が威嚇するように背中を丸めたり逆に反らせたりを繰り返す。
2.【ガス抜きのポーズ】
仰向けになり、両膝を曲げ手で抱え込むようにし、心地よいところで1分ほどキープ。
3.【チャイルドのポーズ】
正座し両手をからだの前について、脱力しながら少しずつ太ももの方へ上体を倒していく。
感動する
感動した時に心拍数が下がり、副交感神経が活発になるという研究結果があるくらい、感動したり涙を流すことは自律神経を健康に保つために良いとされています。映画でも本でも実体験でも、何でもいいので感動するものに触れていくと心も豊かになっていくでしょう。
動作をゆっくりにする
仕事の時はてきぱき動かないと注意されますが、朝起きて家を出るまでの準備や食事などはなるべくゆっくり動くようにします。急いでいるとどうしても慌ただしく落ち着かなくなりがちですが、そこを時間にゆとりをもって動くことで精神的にも落ち着いて心労を減らすことができます。
朝起きたらコップ一杯の常温の水を飲む
起きたときに水を飲むと、腸を目覚めさせて副交感神経が働き、血流がよくなり気持ちが落ち着いてきます。寝ている間に失われた水分を補う、便通を促すという面でも有用です。冷たい水だと内蔵が冷えてしまうので、常温か白湯が良いとされています。
まとめ
自律神経が乱れて深刻な状態になる前にバランスを整えてあげることが大切です。様々な自律神経の整え方をご紹介しましたが、どうしても変えるのが難しい生活習慣や、忙しくてそんなことをしている余裕がない!ということもあるでしょう。一つでも取り入れられそうなものがあったらやってみると心身の変化を感じられるかもしれません。