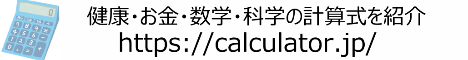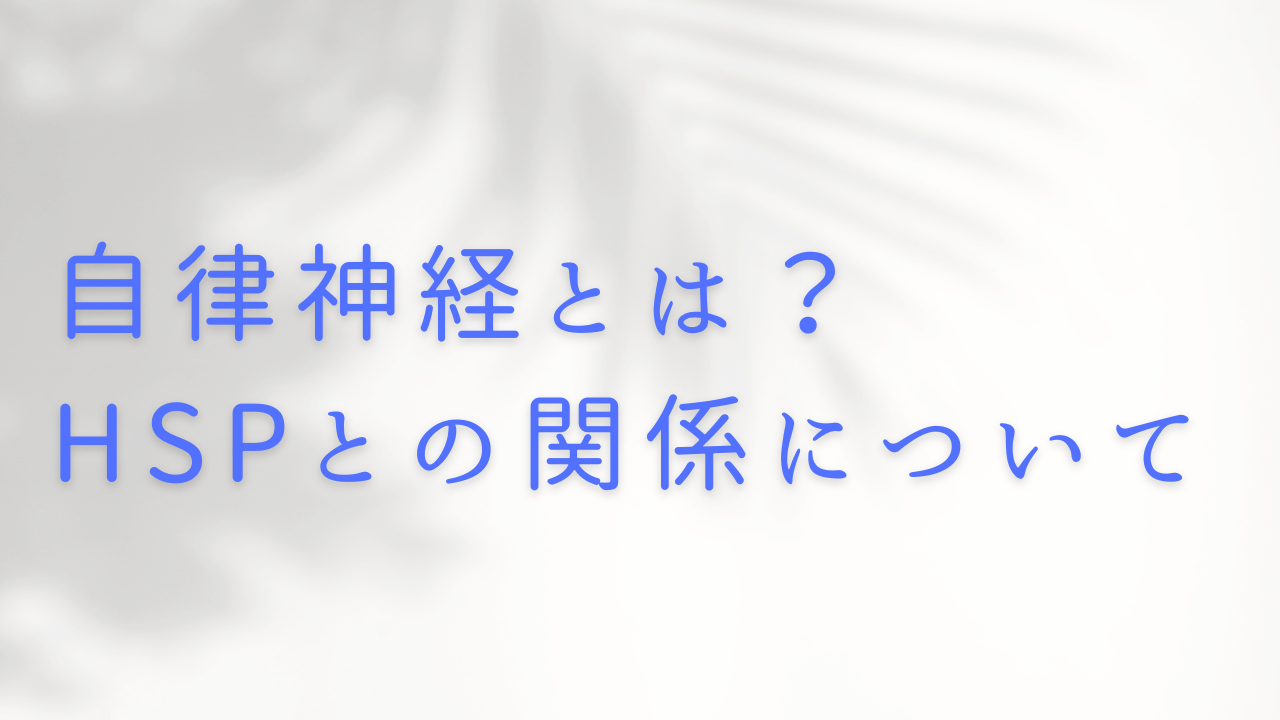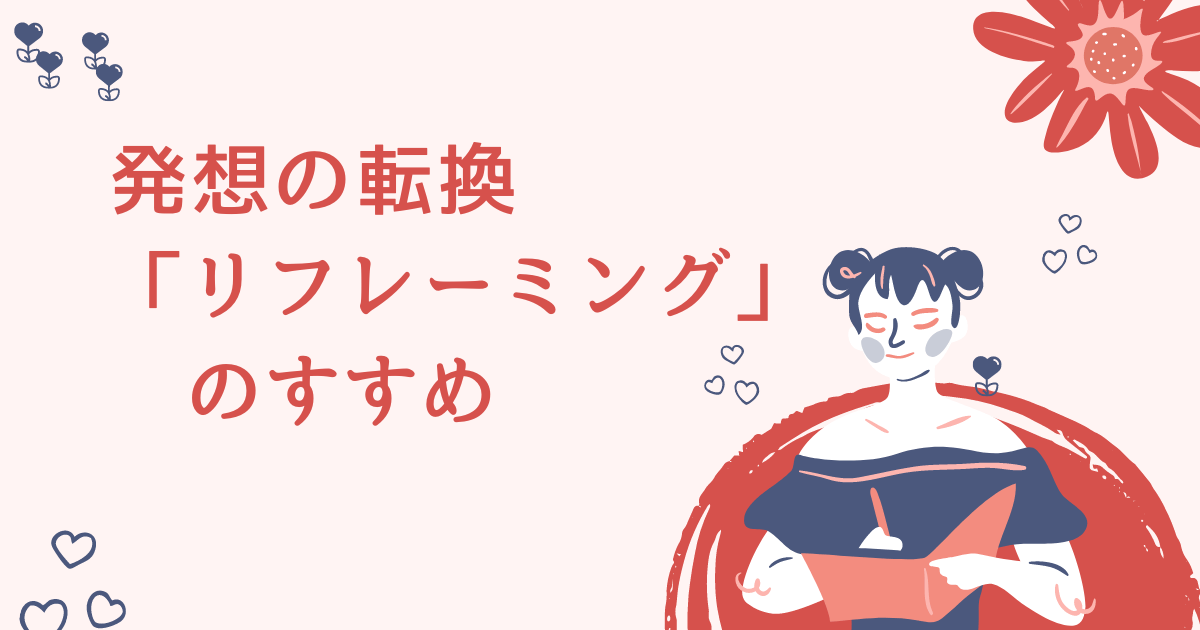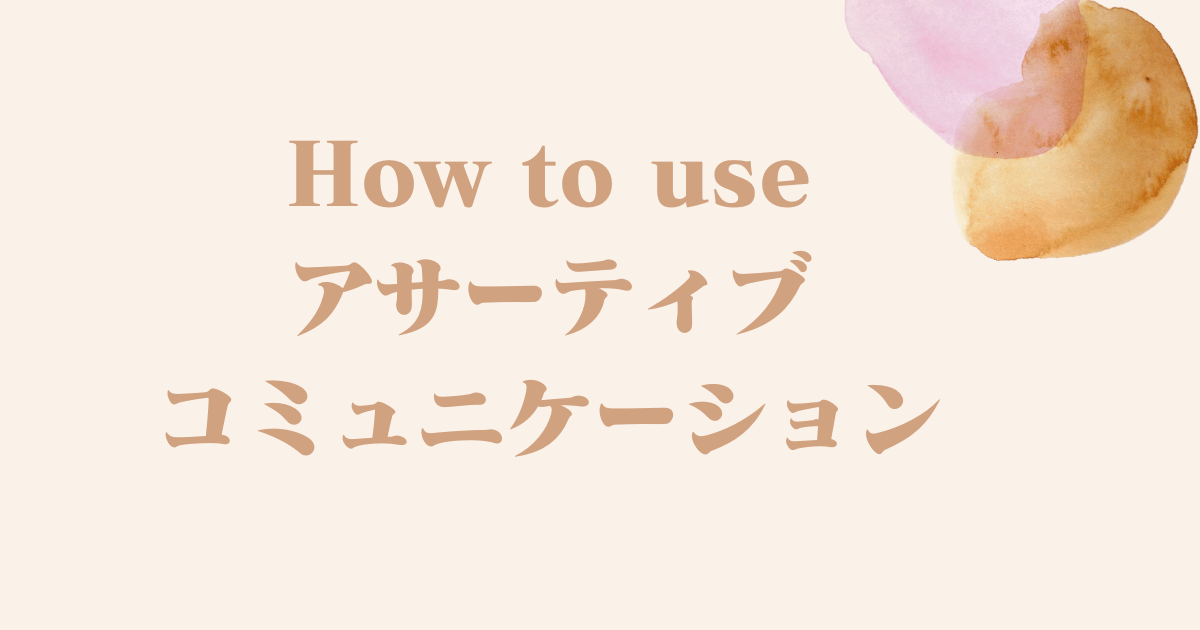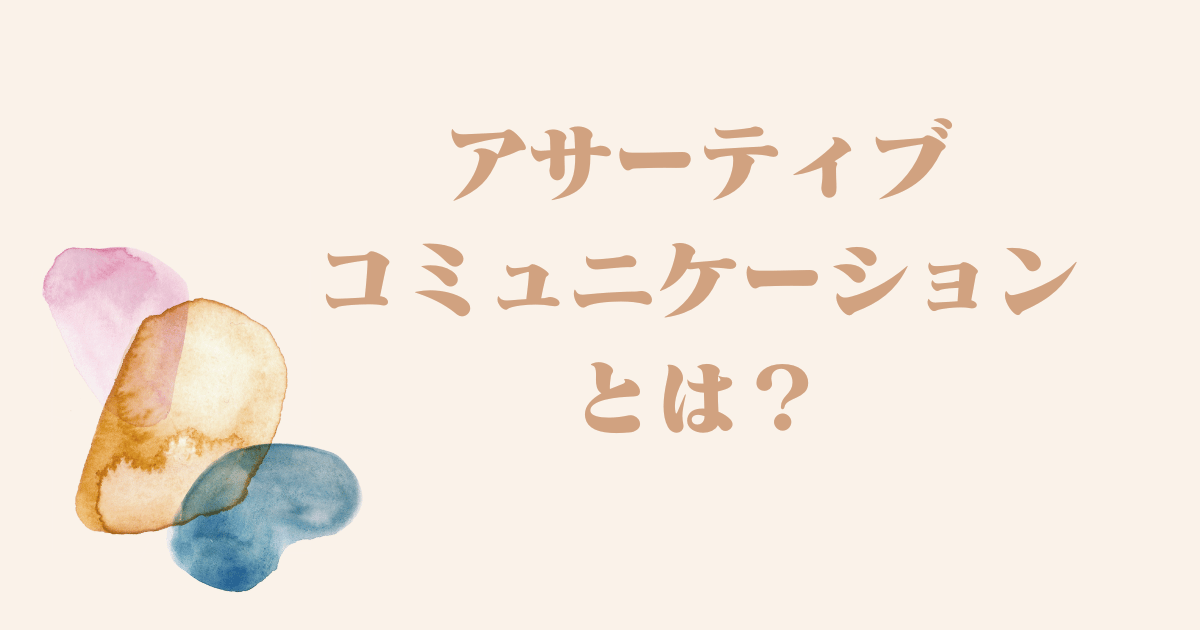人はコミュニケーションから何を受け取っているか?

人は言葉でコミュニケーションをとっているという話(https://sensaikousatu.com/use-cushion-words/)をしましたが、交わすのは果たして話の内容だけでしょうか?
実は、人は「言葉+非言語(言葉以外の情報)」を毎日自分も相手に送っているし、相手からも受け取っています。
非言語にはどんなものがあるかというと、
・表情
・ジェスチャー
・身なり
・声のトーン・声質
・話すスピード・リズム
・声の大きさ
・接触・距離感
・沈黙
・目線
などがあたります。
それらの様々な情報から、
“今日はごきげんだな”
とか
“この話には触れない方がいいのかな”
などと感じ取っているのです。
その証拠に、「今日はごきげんだな」と感じるのはなぜか、どこで判断しているのか考えてみましょう。
「私、今日は嬉しいことがあったの!」と、ストレートに素直に言ってくれれば分かりやすいですが、「おはよう」の声のトーンだったり、鼻歌を歌っている、満面の笑みがあるから等といった非言語の要素で感じることが大きいのではないでしょうか。
言葉そのものも大事ですが、言葉以外の非言語コミュニケーションも重要な情報として受け取っています。
「視線が合わない」「早口でしゃべる」「貧乏ゆすりをする」などの非言語からはどのように感じ取るでしょう?
“あれ、嫌われたかな?私と長くいたくないのかな”と、ほとんどの人がネガティブに感じると思います。
感じるポイントや度合いは人それぞれ差があっても、言葉と共に非言語の情報から私たちは様々なことを受け取ることで、感情が左右されたり、行動する判断基準になったりしています。
複雑なのは、言語と非言語が同じではない時です。たとえ口では「大丈夫」と言っても内心は大丈夫ではない可能性があります。見えない感情を相手の言語・非言語から読み取るわけです。今はLINEや電話、メールなど通信媒体を使ってのコミュニケーションが主になってきていているので、絵文字や、電話であれば声の表情という、直接会って話すよりも限られた情報から相手の感情を読み取ることになります。
よく「大事な話は電話やメールではなく会って直接伝える」と言いますが、直接会うことによって表情や態度などの非言語情報を読みながら相手に合わせて話を進めていったり、伝えたことを相手が誤解して受け取るのを極力防いだり、誠意を示したりするのには、やはり対面で向き合うことが一番だと分かっているからです。
そう考えると、電話対応は本当に難しいでしょう。自分としては普通にしゃべっているつもりでも、電話だと自分の声が違って聞こえる現象が起きます。私も仕事の中に電話対応が入っていて「電話の時は普段より明るめに大きめの声で意識するように」と言われることがありましたが、“素でいけないのは疲れるしめんどくさい”と正直、苦手意識があります。なので、電話対応がそつなくできる方というのは一つの才能だと思っています。
言語と非言語が一致しない時、“そうは言っても腹の中では思ってないでしょ?”と不信感がどうしても生まれてしまいますが、
言語と非言語が一致したとき、自然なコミュニケーションになります。信頼感も生まれます。
コミュニケーションを難しくする原因の一つは、言語と非言語が一致しないことにあると言えます。
これについて実験して法則を見つけた人がいました。次の「メラビアンの法則について」で詳細を述べます。
メラビアンの法則について

メラビアンの法則とは、アメリカの心理学者アルバート・メラビアンが、言語と非言語(実験では非言語を聴覚と視覚に分けている)に矛盾が生じる時、人はどの情報にどれだけの影響を受けるかを実験した結果、言語情報=7%、聴覚による情報=38%、視覚による情報=55%であったというもので、「7-38-55」のルール、または「3Vの法則」とも呼ばれています。
人の第一印象はいつも決まって視覚による情報で半分は決まる、ということではありません。
どういうことか、具体的に見ていきます。
まず、①言語による情報(話す内容)②聴覚による情報(声の抑揚や話すスピード、声量、話し方など)③視覚による情報(顔の表情や目線、外見など)の3つに情報を分けます。
例えば、
①言語による情報(話す内容):「私はあなたに会えてうれしい」
②聴覚による情報(声の抑揚や話すスピード、声量、話し方など):抑揚なく、か細い声
③視覚による情報(顔の表情や目線、外見など):無表情、虚ろな目
→言葉では「私はあなたに会えてうれしい」と言っても、発する声は抑揚がなく、か細い声で顔は無表情、目は虚ろだったら、“本当かな?”と思ってしまいませんか?
3つの情報が一致していなくて混乱するためです。
こうした矛盾が生じた場合に、話した内容は7%、話す声については38%、話す様子については55%の割合で情報を受け取って判断するというのです。矛盾がある場合に55%頼りにするのが視覚による情報(話す様子)というわけです。言語による情報が7%、聴覚による情報が38%なので、2つ合わせたとしても45%、視覚による情報が勝るというわけです。
よってこの例では、言葉はポジティブなことを言っていても、視覚による情報、「無表情で虚ろな目」というネガティブな印象の方が強く持たれてしまうということです。
言語情報=7%、聴覚による情報=38%、視覚による情報=55%の数字だけがひとり歩きして、「人は見た目の方が、話す内容より重要」とか「非言語が言語よりも影響が大きい」といった過大解釈、誤解して伝わってしまっていることがあります。
ですがメラビアン氏が表明したことは、あくまで“自分への相手の気持ちに関すること”で、言語と非言語が矛盾していた時という限定された条件での人が頼りにする情報の割合であって、通常のコミュニケーションでは法則が当てはまるわけではないというのがポイントです。
では、普段のコミュニケーションにおいて、非言語情報はどのくらいの影響力なのか?
アメリカの人類学者・レイ・バードウィステルは、非言語コミュニケーションと『キネシクス( 動作学)』の研究を行った人物ですが、彼は言語が1/3、非言語が2/3の割合で情報を受け取り判断していると結論付けています。
非言語の方が影響の割合は多めなんだ


でも言語も同等に扱う必要があると思うよ
そうね、言葉にしなきゃ伝わらないことだってあるからね
この実験法則から何が言えるかというと、
「どんなに良い言葉を言っても非言語を言葉と一致させなければ言葉による効力が薄れる」、
逆に
「言葉と非言語を一致させれば相乗効果で相手に信頼や安心感を与えられる」ということです。
「すごいすごい」と言いながら拍手をする時、
「すごいすごい!」と抑揚をつけて、拍手も速く、感嘆の表情で表現するのと、
「すごい、すごい」と感情不明瞭に言いながら、パチ・・・パチ・・・パチ・・・とゆっくり拍手するのとでは
褒めているのか、けなしているのか、というほどの差が生じます。
これはあからさまですが、もしかしたら私たちは言語と非言語の不一致によって意図せず相手を不快にさせていることがあるかもしれないということです。
私たちは、疲れて余裕がない時、興味がない話を振られたとき、ついつい非言語としてネガティブな情報を無意識のうち相手に伝えてしまったり、あるいは、相手からのそういった何気ない態度や内心からこぼれ出たちょっとした一言で傷ついたりで、ストレスが溜まり疲れてしまったりしますね。
それだけ非言語は、言葉よりも気持ちに素直に表現されるものであり、感情や好き嫌いが分かってしまうもの、コミュニケーション上の影響が大きいものなのです。
アサーティブコミュニケーションの場合も、どんなにアサーティブな言葉を並べても非言語が伴っていないと伝えたいことが思うように伝わらないので、困っているときは困った顔、嬉しい時は嬉しそうな顔といったように一致させることがとても大切です。
挨拶から始める


生活している中で様々なイベントや状況に置かれ、どんな時でも言語と非言語を一致させるというのは思いのほか難しかったりします。
まずは、『挨拶』から関係の基盤を築いていくのはいかがでしょうか。
当たり前と言えば当たり前ですが、挨拶から交流は始まりますし、挨拶なら「おはようございます」「お疲れさまでした」「おやすみなさい」など、一言程度でもう立派なコミュニケーションとなるので、会話や人付き合いが苦手な人でも実践しやすいと思います。
ちょっとした挨拶でも継続的にしていくと、特に深い話をしたわけではないのに親近感や好意を持つようになり、心地いい雰囲気を作ることができます。これは私の経験上、国内・海外共通でした。
アメリカに短期の語学留学に行った時のことです。同じ語学学校に通う生徒はベネズエラやコロンビア、台湾、フランス、オーストリアから・・・と多種多様でした。母国語が皆違うけど、話したことなくても目が合ったら、すれ違えばスマイルで「Hi!」と声を掛けてきます。日本では見知らぬ人にはまずしないですよね。でも決して嫌な気はしません。むしろ嬉しいです。そんなこともあり、日本でも、職場で違う役割担当によりあまり話すことがない人だけど、出勤するときはよく会うので「おはようございます」は必ず言うようにしていると、向こうからも元気に返ってきました。それを繰り返していくうちにこちらの仕事場に尋ねてきてくれたり好意をもって接してくれるようにまりました。
挨拶はそもそも「私はあなたの敵ではないですよ」とか「あなたを受け入れています」という意味からきていて、その意思表示を毎回していると考えればよい関係を築くために必要なものですね。
でも、やはりここでも非言語コミュニケーションは大事で、ただ挨拶の文言を言えばいいというわけではありません。
「おはようございます」という言葉は同じでも、丁寧に目を見てお辞儀をして挨拶するのと、何かをしながらこちらを見もせずめんどくさそうに言われるのとでは与える印象が違います。挨拶を交わすことでその日一日を気持ちよく過ごそうというのに、後者のような、ネガティブな非言語を用いられての挨拶だと、その日一日モヤモヤしたり気分はいいものではありません。挨拶の本来の目的から離れてしまいます。
苦手とか好き嫌い関係なく挨拶はするもので、気持ちの良いを挨拶し交わし続けると、関係の基盤が作られていきます。一日は挨拶で始まり、挨拶で終わるといっても過言ではありません。
江戸時代の方が他人への配慮があった!?
「江戸しぐさ」というものが一時取り沙汰されたことがあります。
「江戸しぐさ(えどしぐさ)とは、芝 三光(しば みつあきら)[注 1][1]が創作・提唱し、NPO法人江戸しぐさが「江戸商人のリーダーたちが築き上げた、上に立つ者の行動哲学」[2]と称して普及、振興を促進する概念・運動である」
江戸しぐさ – Wikipediaより引用、一部抜粋
言ってみれば、江戸時代のマナー的なものですね。江戸しぐさとして紹介されているものには、狭い道をお互い行き交う時は「肩引き」といって相手とぶつからないように配慮して肩を引くしぐさや、後から他の人が入ってきたときにスペースを座れるようにこぶし一つ分浮かせる「こぶし腰浮かせ」、喫煙場所であっても非喫煙者がいればタバコを吸わない等があります。
しかしこの江戸しぐさ、実際に江戸時代にあったかどうか史実には残っていないため、信憑性が低いとも言われています。もし歴史研究家にでもなっていたら一大事でしょうけども、今この場では歴史上存在していたか否かは問題ではなく、仮に嘘の情報だとしても江戸しぐさの中に確かに存在する「相手を尊重する心意気」が素晴らしいと感じたので、良いと思うものや現代でも生かせそうなものは積極的に取り入れればよいと個人的には思います。
ということで、事実であろうと虚偽であろうと生活の知恵として参考になることはあると思うので、「江戸しぐさ」をいくつか載せておきます。
【時泥棒】
無断でいきなり相手を訪ねたり、待ち合わせ時間に遅刻するなど、相手の貴重な時間を奪うことは重い罪に処せられたという。
【戸締め言葉】
戸とは相手のこころの戸のことで、相手が話しているのに最後までちゃんと聞かないで途中で口を挟み、話の腰を折る。人は、自分の話を聞いてくれない、反論してくる人に心を閉ざすので、そのような言葉(「でも」、「それは違う」、「そうじゃなくて」等)を指す。
【水かけ言葉】
冷たい水をいきなりかけられたように、冷たくあしらわれ、もう話すの嫌だなと思ってしまうような返し。
例)「だから何?」「それだけ?」「ふーん、で?」等
せっかく話したのに取り合ってくれないでシラける返しをされると、「あぁ話さなきゃよかった」と後悔するでしょうし、ストレスが半端じゃないですね。
【陰徳善事】
“いんとくぜんじ”と読みます。「お天道様が見ている」という言葉もありますがそれと似ています。つまり、誰も見ていないからいいやという考えは捨てて、誰も見ていないところでも正しい行い、徳を積むことを良しとするもの。
【うかつあやまり】
自分の落ち度ではないことではなくてもその場の雰囲気を悪くしないように謝る、謝られた方も「こちらの方こそ不注意でした」等とお互いに自分のうかつさを認めること。最初に知ったとき、自分のせいじゃないのに謝るのはストレスが溜まりそう・・・と思いましたが、「うかつあやまり」は相手も謝るため、一方的に責められて理不尽に謝る羽目に陥るのとは違い、モヤモヤはそんなに残らないのではないかと思います。相手も心得ていないと成立しないということで難易度高いですね。
【つかの間の付き合い】
偶然にそこに居合わせた人、初対面で知り合いでない人でも、軽い挨拶やあまり踏み込まない程度の会話をして楽しむこと。「一期一会」、「袖触れ合うも多生の縁」と言いますが、通ずるところがあります。ちなみに私は旅行が好きで、よくツアーで一緒になった人たちと会話をすることがありますが、①ツアー中の雰囲気が和む②様々な情報が得られることがある③後で振り返ったときに何気ない会話や「こんな人がいたなぁ」と、より旅の思い出が深く残っている、という利点を実感します。
江戸時代は今と違い、電車に乗って1時間くらいかけて他県を行き来する通勤や、容易に海外に転勤なんてことはなかったでしょうからその分交流範囲は狭く、その中でうまくやっていかないといけない環境を考えれば、相手に配慮しながら和をもって良しとする文化が生まれるのは自然な流れに思えます。その文化のおかげで一人ひとりが強い絆で結ばれ連携・連帯感もあったのではないかなと思います。
そして今、私もそうですが、満員電車で通勤していて「我先に」と閉まるドアに飛び込み押し合い、席も一目散に座ろうとするのが日常的になっていて、時間的にも精神的にもゆとりのなさを感じます。もう少し情緒やゆとりを持ちたいものですね。