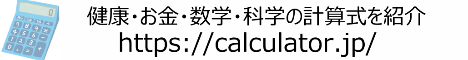こんな方におすすめ
・イライラしやすい
・怒った後に「なんであんなにムキになってしまったんだろう」と後悔する
・怒りの感情の扱いに困っている
怒りについて

最近どんなことにイライラしたり怒りましたか?
その時、どんな言動をとりましたか?
その言動は適切だったと思いますか?
私たち人間は理性的な一方で、豊かな感情を持っていて表現することもできます。
だからこそ複雑な感情を表現する役者や、その演技を見て私たちは物語に入り込んで感情移入できたり、ドキュメンタリーや美しい自然風景などを見て感動したりするわけです。
もちろん、『楽しい』『嬉しい』『感激』『わくわく』などのプラスの感情だけではなく、『悲しい』『不安』『寂しい』『ムカつく』などのマイナスの感情もあり、マイナス感情にばかりとらわれると苦しいですが、かといって感情の一切入らない人生は味気ないでしょう。
怒りは、大脳辺縁系という脳の部位から発動される、原始的で本能的な感情であり、もともと命の危機から守るためになくてはならない感情でした。生きるか死ぬかの危機的状況で、怒りによってアドレナリン、ノルアドレナリンの大量分泌が行われ、全身がフル活動できるよう血の巡りも速くなり、普段以上の力を発揮することがあるのです。
アニメやゲームでキャラクターがダメージを食らったり、ピンチ状態に陥ったりすると、通常出ない必殺技が使えるようになったり、瀕死状態なのに最後に残ったありったけの力を出し切ってボスを倒したりすることがありますが、それと似ているかもしれません。
何が言いたいかというと、怒りそのものが悪いわけではありませんということです。
怒りの感情が起こってしまったことに罪悪感を持つ必要もありません。
ただ、諸刃の剣のように扱いに注意が必要ということです。
瞬間湯沸かし器のような瞬発的な怒りは一時的なものがほとんどで、その一時的な怒りを爆発させたがために取り返しがつかず、後悔することもあるのです。
また、自分の怒りのタイプ、どんなことに怒りを抱きやすいか、対処法を把握することも大切です。
自分の怒りの傾向が把握できれば、怒りポイントの多い環境へわざわざ身を置かないよう未然対策になるし、もし環境が変えられないとしても、メタ認知が働くようになり感情のコントロールが行いやすくなります。
自分の怒りタイプが気になった方は、下記の参照リンクから自己診断することができます。↓
参照:あなたの「怒りタイプ」がわかる。アンガーマネジメント診断(MASHING UP)https://www.mashingup.jp/2017/10/065037anger_type.html
「怒り」は二次感情
アンガーマネジメントに入る前に頭に入れておきたいことが、『怒りは二次感情であること』です。
どういうことか?
二次ということはその前の「一次」があるわけで、一次感情を経て二次感情へつながるという仕組みです。
一次感情とは、怒りの手前の感情(不安、恐怖、寂しさ、心配、悲しみ、辛い、あきれ、虚しさなど)のことです。『怒りの成分』と言ってもいいでしょう。
例えば、
あなたは釣りが趣味で休日は釣りに行くのですが、パートナーからは「ずっと座り込んでじっとしてるののどこが面白いの!?エサも気持ち悪いし・・・」などと言われ、怒りの感情が沸き起こってしまいました。
あなたの中で、何が起こっているかというと、まず一次感情が発生しているはずです。この場合、自分の好きなことをけなされた「悔しさ」「悲しみ」、理解してもらえない「虚しさ」や「寂しさ」などが考えられます。そうした一次感情が積もり重なり、二次感情の「怒り」として表れるのです。
怒る本人も実は自分の一次感情が何であるかがしっかり認識できていないことがあります。
何で怒りを感じているのか、怒りの背景・成分を把握することが相手に伝える上でも、怒る目的を明確にする上でもカギとなってきます。
怒りの性質
1.上から下へ行きやすい
上司から部下へ、先輩から後輩へ、親から子へ、師匠から弟子へ、兄から弟へ・・・など、立場や年齢、経験の差などで上下関係が生まれますが、上流から下流へ流れていく川の流れのように、怒りも上から下へと起きやすいという性質があります。下の方は堪ったものではありませんね。
2.伝播しやすい
周りに、近くに怒っている人がいると話しかけづらいし八つ当たりされるかもしれないし・・・こちらもいい気はしませんね。怒りの感情は他の人にも移りやすいと言われています。
3.身近であればあるほど怒りが強まる
ちょっとした知り合いより親友の方が、赤の他人より衣食住を共にしてきた家族の方が、他部署の人より同じ部署の人の方がお互いによく知っている分、欠点も見えてくるのでしょうか、身近な人ほど怒りの感情は強まる性質があります。
アンガーマネジメントとは

怒りに振り回されずに上手にコントロールするスキルのことです。
怒らないことや我慢することではありません。
怒る必要のあることには適切な相手に適切なタイミングで適切な言葉で伝え、怒る必要のないことには怒らないことであり、そのためには冷静な見極めが重要になってきます。
子供を叱る時や部下・後輩に注意をする時など、頭ごなしに怒鳴るのではなく、相手のためになる叱り方というのがあります。
『「怒ることは誰にでもできる。ただ怒るのは簡単なことである…しかし適切な相手に、適切な程度に、適切な場合に、適切な目的で、適切な形で怒ることは容易ではない。」- アリストテレス』
アンガーマネジメント – Wikipediaより引用、一部抜粋
アサーションやリフレーミングの前に
今にもはらわたが煮えくり返るような状態で、相手の立場になって考えたり相手と穏やかに話し合いができるでしょうか?
無理がありますよね。
まず怒りを鎮めなければ冷静にリフレーミング(https://sensaikousatu.com/learn-to-change-the-way-of-thinking-reframing/)ができないし、怒りの感情の方が勝ってしまい、うまく言語化できないため、相手を尊重したアサーティブコミュニケーション(https://sensaikousatu.com/what-is-assertive-communication/)をとることも難しくなってきます。
怒ることで相手に怒りの感情を伝えることができますが、建設的な話にはなりづらく、下手するとなぜ怒っているのか、怒られたこちらはどうすればいいのかわからないという事態になりがちです。
ただ怒りの衝動に任せて怒るだけだと
「怖い人」
「すぐに怒るよく分からない人」
「近づかないようにしよう」
などと思われてしまい、良い関係が築けなくなる可能性があります。
怒りをコントロールできると・・・

アンガーマネジメントができるようになると、イライラしたことを精査して必要なことだけ怒るため、無駄な怒りで時間やエネルギーをロスしたり、怒りで集中力・注意力が散漫になってミスを招くといったことが減ります。そうなれば仕事の効率も上がり、生活の質は向上し幸福度は上がるでしょう。
また、衝動的に怒ることによりチャンスを失うということが減る、柔軟な考えが養われる、自分が楽になり、周りも平和になるといったメリットが考えられます。
人を指導し導いていく立場の人ほどアンガーマネジメント力は必須だと思います。
そんないいことづくめのアンガーマネジメントのデメリットは、それだけに体得はなかなか難しいという点です。今までの、半自動的に怒る習慣を変えるということにストレスを感じる人もいることでしょう。
それからもう一つ、アンガーマネジメントは『怒りをうまくコントロールする』ことに重点が置かれているため、根本的な問題の解決には辿り着けない場合が往々にしてあります。
アンガーマネジメントで済むケースなのか、問題解決が必要なケースなのかを見極めて対処するのですが、問題解決が必要なケースにしても、怒った状態では正常な判断が下せないので先にアンガーマネジメントで落ち着ける必要があります。
アンガーマネジメントのやり方
すべて網羅しているわけではないと思いますが、比較的取り組みやすく効果を感じられやすいものをいくつかご紹介します。
①6秒は待って
ムカッと来ても、6秒をなんとか乗り切りましょうというのが一つあります。
「6秒」というのは怒りがピークに達するのがそのくらいと言われているためです。なので、6秒間はひとまず怒りの対象から気をそらせることに徹底します。
例)頭の中で10秒数える、何でもいいから掛け算など計算する、壁の模様や周りのものに意識を向ける、(可能であれば)その場を離れるなど
②怒りの分析
イライラしたことを振り返って分析なんて余計イライラする!と思われるかもしれません。ですが、アンガーマネジメントにおいてこの工程は非常に大事なのです。
まず、怒りが湧いたらその怒りに点数をつけます。
10点満点でも100点満点でも、数値化することで今のこの怒りが自分にとってどの程度なのかを把握することが目的です。把握できると客観的視点が意識されて不思議と落ち着いてきたりするものです。
点数付けが終わったら、『何に怒りを感じているのか、それはなぜか』内観し、今自分に怒りの感情があることを受け止めます。
先ほどの釣りの例で見ていきます。
あなたは釣りが趣味で休日は釣りに行くのですが、パートナーからは「ずっと座り込んでじっとしてるののどこが面白いの!?エサも気持ち悪いし・・・」などと言われ、怒りの感情が沸き起こってしまいました。
一次感情の中に「なぜ」の答えがあります。
自分の好きなことをけなされた「悔しさ」「悲しみ」、理解してもらえない「虚しさ」や「寂しさ」などかもしれませんし、あるいは釣りの件とは直接関係のない「仕事のストレス」や「日々の疲れ」、「先日上司に言われた一言に傷ついた」というのも含まれ積もり積もって爆発したということも結構あり得ます。そういう時は今回の件そのものへの怒りとは切り離して考えます。
次に、現状より最悪の状態を考えます。
先ほどの釣りの例でみると、最悪な状態は・・・
『釣り道具を没収され、釣り禁止にされる』
『釣りに行くごとに一万円の罰金が課せられる』
『ケンカして離婚になってしまう』
・・・などといったところでしょうか。うんと最悪なシナリオの方がより効果があります。
最悪な状態を設定した後で今の状況を見てみると、「まだマシな方だ」と思えてきて、怒り度の数値が下がることがあります。どのくらいの数値になったのか、もう一度数値化します。
そして、もしここで自分が取っ組み合いのケンカになってしまったら・・・と、先のことを考えます。
話が少し逸れますが、ニュースを見ていても、後々のことを考えてないため安易に失言や不正、虚偽などが起こっているように感じます。“いずれバレる”、“これを言ったらこれからどんな事態になるだろう”などといった『先を読む力』があればこんなことにはならなかっただろうに、と。
話を戻します。衝動的な感情に引っ張られて、暴言やケンカになったら失うものはやはり大きいです。
それでも構わないのかどうか、自分に問いかけます。
上司にいびられても耐えて耐えて最後に退職するときに、これが最後だからと辞表を『ダン!』と叩きつけて文句の一つ二つ言い放って出ていくとか、怒るにはそれなりの覚悟が必要です。最後の着地点をどこにするか、自分はどうしたいのか、どうありたいのかを定めて理性的に対応するのが『コントロールする』ということだと思います。
数値化もわかりやすいですが、怒りの具合を適した言葉で表現できるようにすることも大切だと思っています。なぜなら、自分の気持ちを伝える時や自分の怒りを把握する時に役に立つからです。
実際に『怒り』にちなんだ言葉を調べると、
立腹・憤然・癪に障る・烈火のごとく・憤怒・憤慨・いらいら・かんかん・むしゃくしゃ・堪忍袋の緒が切れる・へそを曲げる・鶏冠にくる・怒髪天を衝く・眉を吊り上げる・血相を変える・嚇怒・激昂・癇癪・ヒステリック・ぷんぷん・かっか・憂憤・公憤・私憤・憮然など
多くの表現が出てきます。言葉の表現が豊かになると、微妙なニュアンスの違いをより的確に表現できるようになります。
怒ったときに、言葉よりもすぐに手が出てしまったり、関係ない人に八つ当たりや、モノに当たってしまう人は、自分の気持ちをうまく言葉に表現できない苛立ちもあって、モノの破壊や暴力などに向かうのだろうと思っています。
おすすめ『感情ことば選び辞典』
③怒りを一晩寝かせる
一時の衝動や感情で動くとろくなことがありません。
カッとなってすぐに発した言葉には経験上、いい言葉がありません。
後で「ああすればよかった」「あんなこと言わなきゃよかった」と思うこと、あるのではないでしょうか。
一晩(人によっては数日)寝かせると、感情のピークは過ぎて思考は整理され、冷静な判断がしやすくなるので、相手に伝えるのも稚拙ではなく洗練された言葉になります。
一旦時間をおいて、「でもちょっと待てよ、今回の件で自分ができること、自分が変えられることは何だろう?」と考えてみると、
“最近十分に話ができていなかったから今度話し合ってみよう”
とか、
“趣味・好み・価値観が違うんだからそういう意見もある。いちいち腹を立ててたらキリがないから、今度言われても軽く流そう”
など対策が出てくることがあります。
楽しいことで気晴らしする形で、その件から離れてみるというのも効果があるようで、怒り度がピーク時より下がっていることが実感できるでしょう。
ただ、私を含め、すぐに怒りの感情を切り替えるのがなかなかできない人もいると思います。
そんな私が試みていることとしては、
1.相手に期待しすぎない
どんなに「いい人」とか「気が合うな」と思っても、期待しすぎないこと。期待しすぎると、相手だって完璧じゃないのに「この人なら絶対分かってくれる」「この人は絶対そんなことしない」など、自分の中で偶像を作ってしまう。そして、いつか何かの節でその偶像にひびが入るような出来事が起こると「裏切られた」とか「信じてたのにショックだ」「そんな人だったなんて・・・」となってしまう。だったら初めから過信しない方がいい。
2.近すぎない関係を意識する
「水くさい」くらいの距離感が、結局は嫌な部分が見えて腹を立てることがなく上手くいく。怒りの性質の一つ、「身近な人に怒りがいきやすい」を避けるためでもある。「親友」とは、「いつでもどこでも一緒」とか「依存し合っている」わけではなく、個々は自立していて、離れていても理解し合っていて、大事な時には打算のない「絆」を発揮する間柄というのが持論。
3.敬意を払う
「親しき中にも礼儀あり」。仲良くなるほど口調も崩れていきがちで、それが自然で心地よければいいが、相手の心の距離感と自分の心の距離感との間にギャップができている場合だってある。そういう場合、「なんであなたにそんなことを言われなきゃならないの?」とか「馴れ馴れしい」などと感じてしまうため。
です。
家族で血がつながっていても、違う人間だしそれぞれの価値観を持っています。にもかかわらず、自分の価値観を押し付けようとしたり敬意を払わなくなるからケンカや事件が起きるのでは?と感じています。
おすすめの本
怒りについて大々的に書かれているわけではありませんが、人生や生活に対する姿勢・考え方などが腑に落ちて気持ちが楽になったり、奮い立たせてくれた本をご紹介します。
1.『白洲次郎100の言葉 逆境を乗り越えるための心得』
生きざまがカッコいい人は、思考も行動も発言もカッコいい!私もこういう人になりたいと素直に思えた人。功績も素晴らしいけれど、才能、手腕に加えてその背景には彼の美学や信念があって、その部分をもっと多くの人が知って感銘を受ければ世の中もだんだん良くなりそうな気がします・・・。
2.『ブッダが教える 執着の捨て方』
熱心な仏教徒ではないですしこういった類の本はたくさんありますが、この本は腑に落ちてスッと入っていく。本の内容を忘れたころに心が折れたり、囚われていたりするけど、もう一度部分的にでも読み返すと『あぁ、そうだった・・・!』と初心に帰ることができました。
怒りとEQ

頭の知能指数であるIQに対して、EQとは『感情をコントロールして相手の感情をも読み、うまく利用する力』(こころの知能指数)と言われています。
このEQを高めることがビジネスにおいては成功のカギとなり、生活においても質を高めることに繋がります。幸いなことにEQは、今からでも向上させることが可能です。
EQが高い人の特徴の一つとして、『感情のコントロールがうまくできること』が挙げられます。扱いが難しい怒りのコントロール、すなわちアンガーマネジメントが上手くできる人はEQが高い傾向にあるでしょう。
こちらの本では自分のEQを測ることができ、体系的にEQについて学ぶことができます。↓
『EQ こころの知能指数2.0』