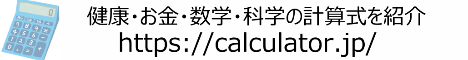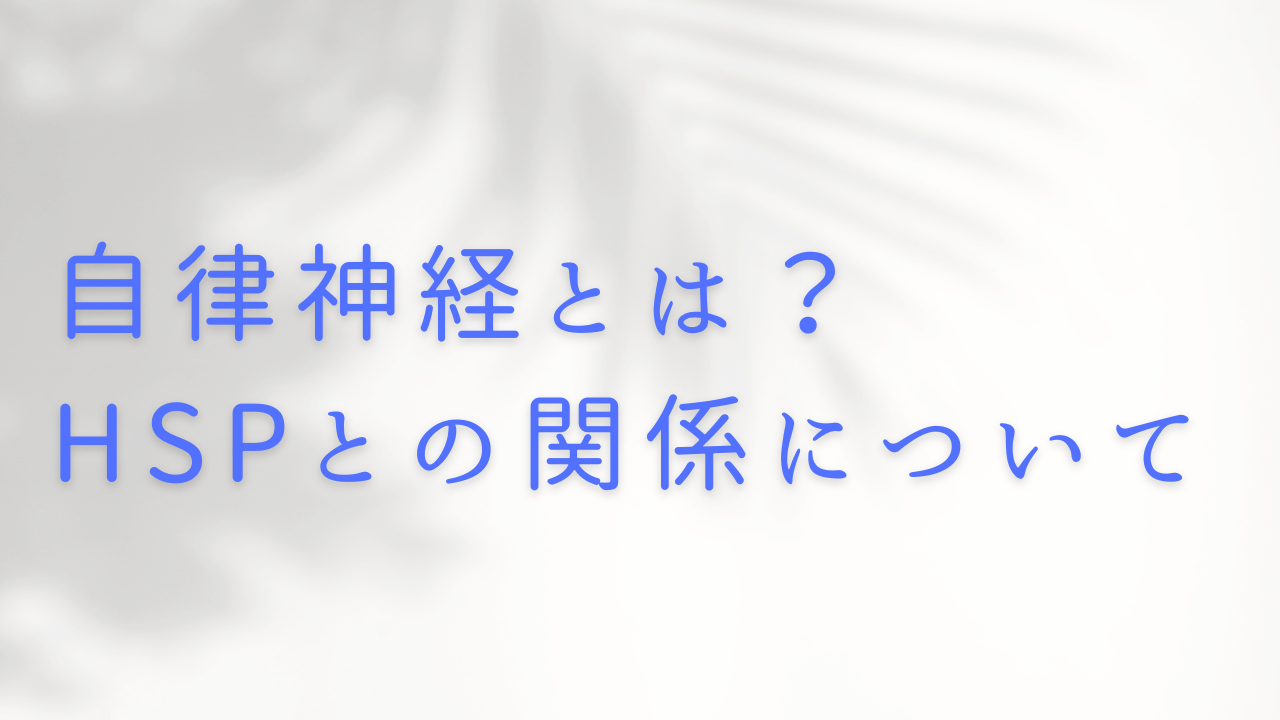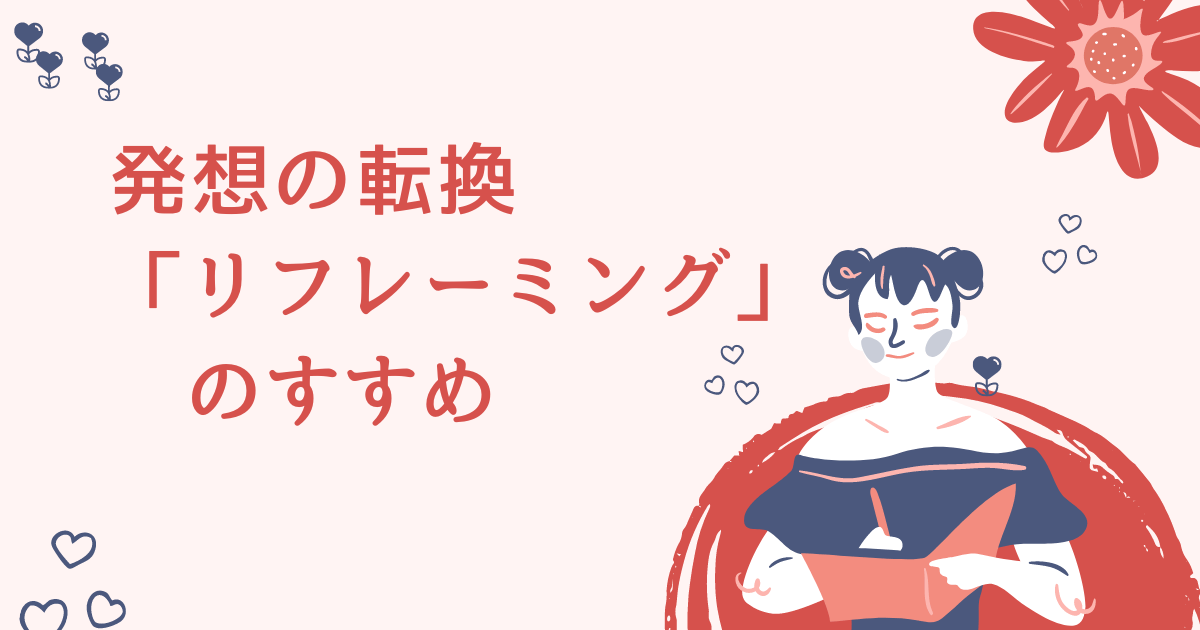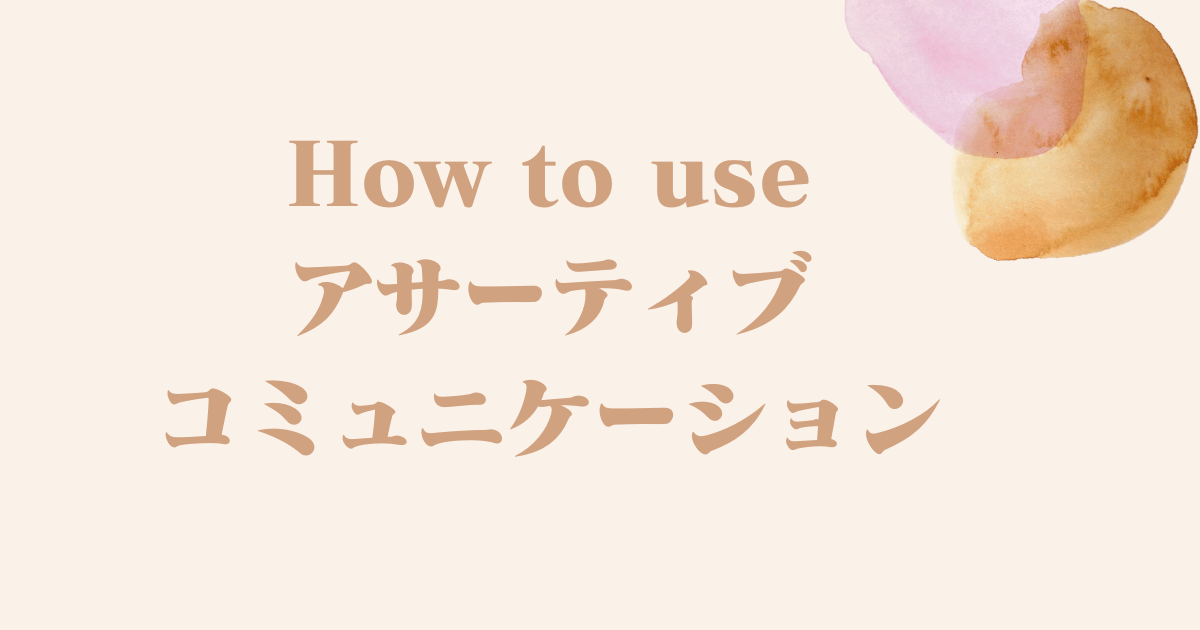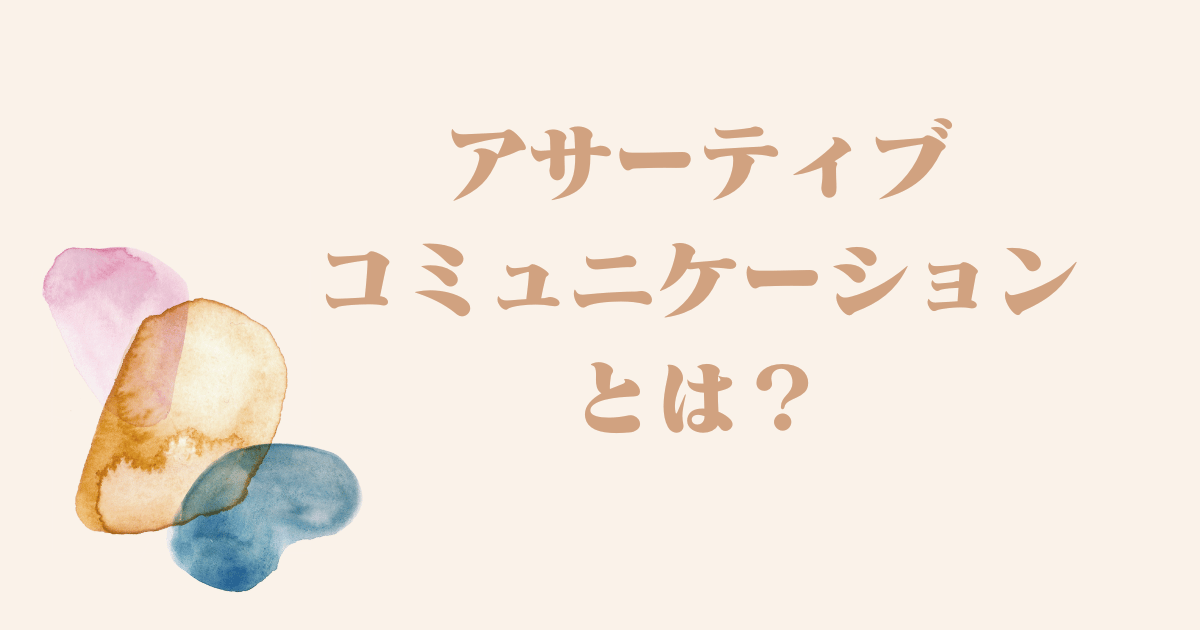今までの記事にもしばしば「ストレス」の字が登場することがありましたが、
そもそもストレスって何なのでしょう?
その正体は?
改めて考えると疑問がいろいろ湧いてきませんか?ストレス社会で『ストレス』と向き合うにはしっかりと理解しておかなければいけないことなので、いまさら聞けないストレスのことを解説していきます。
ストレスとは?

当たり前のように使っている言葉でも、いざ「説明して」と言われると、漠然としていてうまく説明できないことがあります。改めて「ストレス」について調べてみると、丁寧な説明が出てきます。
『外部からの刺激などによって体の内部に生じる反応のこと。その原因となる外的刺激(ストレッサー)とそれに対する私たちの心身の反応(ストレス反応)とを合わせてストレスと呼ばれることもある。・・(省略)・・ストレスの原因となる外的刺激をストレッサーといい、これを含めてストレスと表現されることもあります。ストレッサーには、暑さ寒さや有害物質など物理的・化学的なもの、病気や飢え・睡眠不足などの生理的なもの、職場や家庭における不安・緊張・恐怖・怒りなど心理的・社会的なものなどがあります。人間では特に心理的・社会的ストレスが大きいとされています。』
ストレス | e-ヘルスネット(厚生労働省) (mhlw.go.jp)より引用、一部抜粋
本来は物理学で使っていた言葉で、生理学にも応用され、「ストレス学説」が唱えられ、今のような使われ方になったという経緯があります。
ストレスは外からの刺激によって生まれる、言われてみれば確かにそうだね。


外からの刺激を「ストレッサー」と言ってストレスの元となるよ
そうとは知らず、ただイライラする・疲れることをひっくるめて「ストレス」って言っていたよ
ストレッサーの種類
日々の生活で実感していると思いますが、ストレスの元となる「ストレッサー」は多種多様です。
【物理的ストレッサー】
目からの刺激(照明や日光、電子機器のディスプレイの明度、彩度など)耳からの刺激(騒↔静、高↔低)気候や空調(暑い、寒い、ジメジメする、乾燥するなど)
【心理・社会的ストレッサー】
仕事(〆切やノルマなど)や学校生活、家庭、ライフイベント(入学、卒業、受験、進学、就職、転職、引っ越し、結婚、妊娠、子育て、冠婚葬祭、介護など)」、人間関係、人との関わりによるもの、経済的な問題、情報過多。心理的なものは、主に自分の内的な感情(不安、恐れ、いらだち、寂しい、焦り、心配など)を指し、他のストレッサー、特に社会的ストレッサーである人間関係と関わりが深いとされています。
【生理的ストレッサー】
睡眠不足、空腹、疲労、病気、感染(細菌やウイルス)、アレルギー、生理、痛み、かゆみなど
【化学的ストレッサー】
タバコやアルコールなどの化学物質、食品添加物、金属、車や工場などからの有害物質、においのきつい香水などによる鼻や目、喉への刺激、空気(酸素濃度)など
※ちなみに、『外的刺激』をストレッサーと書きましたが、細かく分けると内的刺激というのもあり、
外的刺激・・・『物理的ストレッサー』や『化学的ストレッサー』『社会的ストレッサー』のような自然や社会環境からくるもの
内的刺激・・・『心理的ストレッサー』『生理的ストレッサー』のような個人的なもの、自分の中で発生しているもの
に分けられます。
ストレスを受けると・・・
これらのストレッサーからストレスとして感じ取ると、ストレスに対して様々な反応が起こります。
ストレス反応は人それぞれで、「苦手な人との関わりによる胃痛」「空腹によるイライラ」「寝不足による集中力の低下」「緊張感による過呼吸」「クレーム対応で血圧上昇」・・・など多岐にわたりますが、大きく以下の3つに分けられます。
【心理的反応】
落ち込み、思考・判断・集中力・意欲の低下、食欲減退、不安、、緊張、焦りなど
【身体的反応】
胃痛、嘔気、過呼吸、発熱、肩こり、動悸、頭痛など
【行動反応】
ケンカ、引きこもり、過食/拒食、アルコールやタバコの多量摂取、ギャンブル、泣く、自傷行為、問題行動など
大なり小なり、刺激はすべてストレッサーとなり得ます。
ストレス状態が続いてひどくなると、病気になったり、自律神経の乱れなど、健康を脅かすリスクがあります。
また、自分ではストレスとして感じていなくても知らず知らずのうちに疲労として出ていたりします。例えば、旅行に行くときや楽しんでいる時は全然疲れを感じなかったけど、帰りの列車で、あるいは家に着いたとたんどっと疲れる、なんてことありませんか?
ストレスの感じ方や度合い、ストレスを受けた後の心身の症状や行動も人によって違いがあります。
まだ大丈夫と思って頑張っていたらいつかダウンしてしまうこともありますので自分の状態を的確に把握し、心身を十分に休ませることが大切になってきます。
ストレスに対処するには?


“ストレスはなるべくない方がいい”
ストレスについてネガティブなイメージが強いので、そう思うのは自然ですね。
ストレスをもろに受ける、受け続けると、心身が疲弊する、病気のリスクも出てくる・・・
生活している限り、ストレスを全部なくすことは不可能ですが、軽減したりストレスを味方につける方法はあります。
ストレスへの対処法として、①「発散」②「発想の転換」③「問題解決」④「アンガーマネジメント」の4パターンをお伝えします。
(※ここでは、そういう方法があるということだけに留めて、別の記事で具体的に書いていく予定です。)
①発散
ストレス解消として行っていること、例えば、「睡眠」「読書」「ヨガ」「カラオケ」「買い物」「深呼吸」「瞑想」「旅行」「愚痴を言う」「甘いもの、美味しいものを食べる」等々、人によっては、お金を使いたくない人、疲れているのに外出したくない人などそれぞれですし、効果も異なります。休日にできるものから仕事の休憩中にできるものなど、時間単位で「今この状況ではこれ」と決めておくのもいいでしょう。今のところまだ発散できていないという人は、これから色々と試して自分に合った発散法を見つけていきましょう。
②発想の転換(ストレス耐性)
ストレスの感じ方や度合い、ストレスを受けた後の心身の症状や行動も人によって違いがあるとお伝えしましたが、この違いは『ストレスへの抵抗力・耐えうる力の差』が関係しており、ストレスへの抵抗力・耐えうる力を『ストレス耐性』と呼びます。
ストレス耐性が高い=ストレスへの抵抗力・耐えうる力が強い、ストレス耐性が低い=ストレスへの抵抗力・耐えうる力が弱い
ということです。
ウイルスへの免疫力を高めるためにワクチンを打つように、あるいは、筋トレをして筋力体力をつけるように、ストレス耐性を高めることはできないのか?
結論から言うと、可能です。
筋トレみたいにハードなトレーニングが必要?
ただストレスにひたすら耐えればストレスへの免疫がつくってこと?
いいえ、ストレス耐性をつけるのにストレス過多になってしまっては本末転倒です。
カギとなるのは『考え方、捉え方』です。ストレス耐性は『②発想を変える』に関連しています。
同じことが起きても、余裕がなくて周りに不穏な空気をまいてピリピリしている人と、余裕があり冷静に穏やかに対応している人と、刺激への反応が違うことがあります。
“これは性格だから”とあきらめてしまうところなのですが、物事に対する『考え方、捉え方』による部分が大きく、これは自分次第で変えていくことができるのです。
ライバルがいると負けじと頑張るのと同じ原理で、ストレスが自身を奮い立たせてモチベーションになることもありますが、そのように上手くストレスを自身の原動力に変えられる人はストレスの適応力、ストレス耐性が高い人と言えるでしょう。
③問題解決
やっぱりストレスを発散したとしてもまた同じことが起きたらストレスも同じように溜まって繰り返してしまうという場合、それは根本的な解決にはならないので、解決の余地がありそうなものであれば問題解決にあたったほうがよいでしょう。
例えば、
「いつも仕事でし忘れることがある」→ToDoリストを予め作っておいて見ながら進める、付箋を貼る、アラームをセットするなど
「仕事が遅くて残業になる」→優先順位をつけて取り掛かる、無駄がないか・必要ではないことに時間をかけすぎていないかチェックする、要領よくやっている人の仕事の仕方を参考にするなど
また、解決法の一つとして、自分一人では解決できない問題については「人に相談する」という場合もあるかと思います。愚痴るのとは違って相手が直属の上司やあまり状況を良く知らない第三者で、誤解なくうまく伝える必要がある時はアサーティブコミュニケーション(https://sensaikousatu.com/what-is-assertive-communication/)を使うのがおすすめです。
④アンガーマネジメント
聞いたことがある人もいるかもしれません。怒りをコントロールすることです。
怒りとストレスは密接な関係で、一緒のように扱われることが多いほどです。
ストレスがかかった状態だと怒りやすくなりますし、怒られることもストレスになる。怒りを我慢してもストレスが溜まります。
怒りを爆発させればその時は胸のわだかまりがなくなって爽快な気分になるかもしれませんが、一時的な感情に任せて怒ることは、後悔や人間関係の修復の困難さにつながるため注意が必要であり、その怒りをコントロールすることで、ストレスもコントロールしていきます。
まとめ


ストレスやストレスの仕組みについて理解は深まったでしょうか?
「ストレッサー」、「ストレス」、「ストレス耐性」の概念があると、理論的な話になって冷静に対処できそうに思えてきます。
扱いにくいストレスですが、溜めすぎて爆発して後悔しないように日ごろから少しずつでも発散したり、解決に向けていったり、捉え方を変えてみたりしながら上手く付き合っていきましょう。